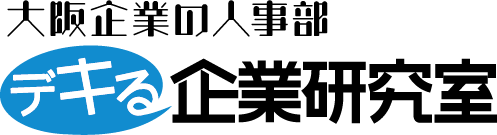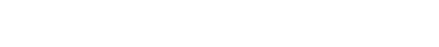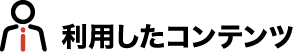水道業
大阪支店 総務課の皆さん・右手前が今出さん
下水道管の維持管理・「人のために働く」人と職場を伝えたい!
公共性の高い仕事が強み
合同企業説明会を積極活用
ミスマッチ予防と定着の取組み
- 人材採用・定着のための3つのツール
- マッチングイベント(求職者・学生との交流会・合同企業説明会等)
管清工業株式会社
大阪支店 総務部総務課 今出 安里紗
設立:設立:1962年10月4日
従業員数:全社:647名(2024年6月末)
貴社の会社概要と求職者に伝えている職場環境や社風について教えてください。
今出氏:当社は人々の生活に欠かすことのできないライフラインの一つである、下水道管の維持・管理などを行っています。とても公共性の高い仕事であり、使う人の立場に立ち人のために役立ちたいと思っている人がたくさん働いています。求職者はほとんど未経験者なので、仕事にきついイメージを持たれがちですが、私たちは下水道管の維持管理に最先端のロボット技術やシステムを活用しており、ライフラインを守る重要な仕事であるという会社の思いを伝えています。そして、応募前に職場見学をしてもらい、現場で働く従業員と対話をしてもらうなど、納得して応募してもらうような環境をつくる努力をしています。
OSAKAしごとフィールドの支援メニューを活用するようになった経緯を教えてください。
今出氏:私が大阪支店の採用担当になった5年程前は、新卒採用に重点を置き活動をしていましたが母集団を増やすことに苦労していました。また、既卒や中途採用にも取り組みましたが、ハローワークや求人広告でもなかなか成果には結びつきませんでした。そのような状況下にインターネット検索で、2024年開催OSAKA JOBフェア(業界研究会・合同企業説明会)の出展企業募集の広告を偶然見つけ、そのイベントの主催者であるOSAKAしごとフィールドの存在を知りました。さらにOSAKAしごとフィールドでは、交流会の企画運営や、採用に関する企業向けセミナーをしていることも知りました。2024年開催OSAKA JOBフェアは、インターネット広報や公共交通機関への広報を積極的に展開されていたので、出展申込をしてからイベント当日を迎えるまでOSAKAしごとフィールドに対する期待感や信頼感、安心感を抱いたことを記憶しています。
どのようなOSAKAしごとフィールドの支援メニューを活用しましたか?また、活用した際の成功事例はありますか?
今出氏:OSAKA JOBフェア(2024年2月開催・2025年2月開催)に2年連続で出展しました。2024年2月のOSAKA JOBフェアでは、業界研究会でブースに来てくれた大学3年生が、当社の職場体験にも参加してくださり、現場の見学や働く社員との交流を通じて、さらに当社の仕事を理解してくれました。その後その学生は選考に進み、2025年4月1日に入社してくれることになりました。とても嬉しかったです。2025年2月のOSAKA JOBフェアでは、事前開催されたオンライン合説でブースに来てくれた既卒者が、後日の来場開催当日に、真っ先に私たちのブースに来てくれました。当社の公共性の高い仕事、公共事業に関われることに興味を持っていただき、その後選考に進み、先に説明した方と同じく、2025年4月1日に入社してくれることになりました。このように2年連続で成果が出ており、OSAKAしごとフィールド主催の合同企業説明会は、信頼感や期待感があり、今後も参加したいと考えています。また、私たちはイベント出展などの母集団形成の取組みと並行して、入社してからミスマッチに気づくことが無いよう、職場見学や社員との懇談会を通して仕事、職場、そして一緒に働く社員の人柄を理解してもらう機会を充実させています。この取組みには、忙しい現場の皆さんの協力が不可欠です。現場の皆さんは、今の採用難の状況を理解して、積極的に協力してくれており、本当に感謝しています。
今後どのような取り組みに注力したいと考えていますか?
今出氏:「今いる社員を大切にする」ことが大切だと思っています。つまり定着率を高めることです。
今の採用活動と並行して、働きやすさの制度見直しにも取り組んでいきます。多様な働き方が求められている現在、社員の働き方を支えるための制度整備を行うことで、なるべく長く働いてもらうことが可能になると思います。社員が活き活きと働き、その魅力を発信することで、採用に繋がる好循環を生み出して行けたらと考えています。2025年度より定年年齢を60歳から65歳まで選択できる制度も取り入れ、長く働ける環境も準備していこうと思います。